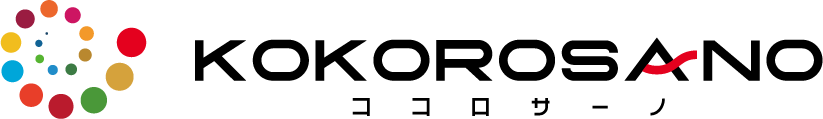「怒り」をマネジメントすることと、部下や後輩、チームメンバーたちに対して何も言わないことは、決して同義ではありません。
ビジネスの現場で問題が生じた場合など、伝えるべきことは伝えなければなりません。
そんな時、相手を威圧することなく、必要なことを上手に伝える方法をご紹介します。
そもそも怒るのではなく、「注意」「指導」するという考え方について
前章(「怒る状況を作らない予防策」や「怒らない為のメソッド」)では、「怒り」や「イライラ」から生じる、パワハラ事件につながる可能性のある言動への予防・対策方法について、具体的に見てきました。
しかし、ビジネスの現場において、マネージャーが常に優しく、温和で、ニコニコしていれば良い、というものではありません。
「ビジネス現場でマネージャーが求められることについて」でも触れましたが、マネージャーが求められることとは、与えられた(限られた)環境と人材を活かし、最大限の成果を上げることです。
その為には、時には、部下や後輩、チームメンバーたちにとって、耳に痛いことを言わなければならない場面もあるでしょう。状況によっては、強めに伝える必要も出てくるかも知れません。
ここで、彼らの反応を気にし過ぎるあまり、何も言えなくなってしまうと本末転倒です。
重要なことは、「適切に」「冷静に」相手に伝えることです。
人間は、感情的な態度を取られると、受け手側も感情的になります。
あなたが相手に対して「怒り」の感情を持ったとしても、適切に表現することで、上手く自分自身の感情や態度をコントロールしてゆきましょう。
その為に重要な考え方として、そもそも怒るのではなく、業務遂行に必要な「注意」や「指導」を行う、と考えてください。
ちなみに、逆に、マネージャー側が部下や後輩、チームメンバーたちから圧力をかけられて、業務遂行に支障が出るような場合は、「パワハラの3要素」に則り、「逆パワハラ」となります。
パワハラは上から下への一方通行ではありませんので、話し合い等で解決しない場合は、事態が悪化する前に、上司や人事部へエスカレーションするなどの対策を取りましょう。
上手な気持ちの伝え方について
部下や後輩、チームメンバーたちに対して、業務遂行に必要な「注意」や「指導」を行う場合の、上手な気持ちの伝え方をご紹介したいと思います。
おすすめ
上手な気持ちの伝え方として、『具体的な実行方法』や『注意ポイント』などを、電子書籍により詳しく掲載しています。
ご興味のある方は、「オンラインストア」をご覧ください。
上手な伝え方① 常に話に一貫性を持たせる
一番重要なポイントとなりますが、「注意」や「指導」を行う場合、相手にもしっかりと理解・納得できるように伝える必要があります。
あなたが伝えたいと思った背景には、客観的に見て問題がある場合や、業務遂行上、あなたが守るべきと考えている指針(ポリシー)に反する場合などがあるかと思います。
その場合の基準が一貫していれば、例え「ちょっと厳しい上司だな」と思われたとしても、部下たちも納得できますし、できる限り、その指針に沿ってゆこうとするでしょう。
上手な伝え方② ゆっくりと落ち着いて、明確に伝える
いくら頭では「注意」や「指導」だと思っていても、「怒り」や「イライラ」が生じている場合、気持ちはたかぶりがちです。
その為、伝えたい話がある時ほど、意識して、ゆっくりと落ち着いて話すことを心がけましょう。
また、明確に、内容を伝えることも重要です。
あなたが指示を出す際、どうしても守って欲しい(実行して欲しい)指針(ポリシー)があるならば、予め、明確な言葉で伝えましょう。
不必要な摩擦を避ける結果となりますし、何よりも業務遂行において効率的です。
上手な伝え方③ 適切なタイミングで、わかりやすい言葉で伝える
何か問題が生じた際、「注意」や「指導」を行うタイミングも大変重要です。
問題発生時、もしくは発覚時に、明確に伝えられると、受け手としても腑に落ちやすく、納得感につながります。
しかし、時間が経ってから、何件かまとめて指摘をされても、当時の感覚や記憶も曖昧になっていますし、「どうして今頃…」と思いがちです。場合によっては、理不尽な言いがかりを付けられたような気持ちになって、反抗的になってしまうかも知れません。
また、その際に、わかりやすい言葉で具体的に伝えることもとても重要です。
上手な伝え方④ 「私」目線の「I(アイ)メッセージ」で伝える
コミュニケーション方法の一種に、「I(アイ)メッセージ」と「You(ユー)メッセージ」があることをご存知でしょうか?
普段、あまり意識せずに相手に話しかけていることが多いかと思いますが、この2種類には、以下のような違いがあります。
- I(アイ)メッセージ:主語は「私」→「私」の気持ちを主体として伝える方法
- You(ユー)メッセージ:主語は「あなた」→「あなた」の言動を主体として伝える方法
「I(アイ)メッセージ」は主語が「私」となる為、あくまで話し手側の意思を主張するに留まりますので、相手を尊重し、攻撃しないコミュニケーション方法となります。
逆に「You(ユー)メッセージ」は主語が「あなた」となり、相手の状況や言動をダイレクトに指摘する形となる為、攻撃的なニュアンスを感じさせやすいコミュニケーション方法となります。
相手に少しでも、あなたの気持ちや意図を落ち着いて聴いてもらう為に、「私は〇〇と思っている」「私は君に〇〇して欲しい」「私は〇〇してもらえると嬉しい」というような「I(アイ)メッセージ」を意識して使ってゆきましょう。
上手な伝え方⑤ 原因究明だけでなく、今後の対策や相手の考えにも耳を傾ける
何か問題が生じた際、原因を究明し、再発防止に努めることは、企業にとっても現場にとっても、必要なことです。
問題があったことは相手と共通認識を持ちながらも、それを踏まえて「いかに改善してゆくか」にフォーカスし、ともに前へ進もうとする姿勢をあなたが部下たちに見せることで、相手もあなたの声を受け入れやすく、より良い関係性を築きやすくなります。
もちろん、あなたが相手に求める明確な内容もあるかと思います。
その時は、問題や失敗に言及するのではなく、今回の話し合いの場をきっかけとし、「今後の要望」として、相手に伝えましょう。その際、具体的な理由を添えると、尚良しです。
ちょうど相手側も話を聴く体制ができている場ですから、スムーズに伝わりやすくなります。
上手な伝え方⑥ 関係者を招集し、全員の問題として解決を目指す
タカラトミーの「黒ひげ危機一発」というオモチャをご存知の方も多いのではないでしょうか。
海賊が入った樽に、剣を順番に刺してゆき、海賊を飛び出させてしまった人が負けというパーティゲームです。
チームで仕事に取り組む際、このゲームと似たようなことが起きることも意識しておきましょう。
つまりは、ある個人が一人で問題を起こすこともあれば、チーム内の仕事の仕方によって徐々に積み上がってきていた問題を、ある日、誰かが引き当ててしまうこともあるということです。
その際、ババを引いてしまった人が不利な状況とならないよう、また、誤解を受けることもないよう、冷静に説明することが重要です。その為にも、客観的な情報を添えて説明することが重要となります。
その上で、みんなで解決してゆこうとする姿勢をあなたが見せることにより、まわりもあなたの声を受け入れやすく、より良い関係性を築きやすくなります。
振り返りとフォローアップの重要性について
部下や後輩、チームメンバーたちに対して、業務遂行に必要な「注意」や「指導」を行った場合、後から自分自身の言動について振り返ることも重要です。
どんなに意識していても、「怒り」や「イライラ」がわいてくると感情的になりがちです。
その為、あなたの気持ちや意図を「適切に」「冷静に」相手に伝えることができたか、クールダウンした後に必ず、振り返ってください。
もし、「さすがに言い過ぎた」「やり過ぎた」と感じた場合は、その点に関しては早急に謝罪し、本来の意図を丁寧に説明し直しましょう。
相手もいきなり呼び出されたら警戒するでしょうから、最初はメールを送り、その後、できる限り、第三者に同席してもらって直接、話し合いの場を設けてもらいましょう。
また、振り返ってみて、もし、今回、行き過ぎはなかったと判断した場合でも、相手に対して継続的に、励まし、ねぎらい、勇気づけることを忘れないでください。
これらの行動は、相手に対して真摯に接する上で、大切なことです。
マネージャーとして、チームや組織の中で信頼される為にも、とても重要なことです。
しかし、それだけではなく、万が一、あなた自身がパワハラ容疑者として名前を挙げられた場合、あなたの日頃の態度を見極める材料のひとつとして、これらの対応履歴も取り上げられることでしょう。
あなた自身の身を守る上でも大切な取り組みであることを覚えておいてください。
まとめ
「上手な気持ちの伝え方」について、まとめ情報は以下の通りです。
この記事のまとめ
- そもそも怒るのではなく、「注意」「指導」すると考え、重要なことは「適切に」「冷静に」相手に伝えること。
- 「注意」「指導」後の振り返りとフォローアップは、チームメンバーとの信頼関係を築く為にも、自分自身を守る為にも重要。
- 上手な気持ちの伝え方のコツは以下の通り。
- 常に話に一貫性を持たせる
- ゆっくりと落ち着いて、明確に伝える
- 適切なタイミングで、わかりやすい言葉で伝える
- 「私」目線の「I(アイ)メッセージ」で伝える
- 原因究明だけでなく、今後の対策や相手の考えにも耳を傾ける
- 関係者を招集し、全員の問題として解決を目指す